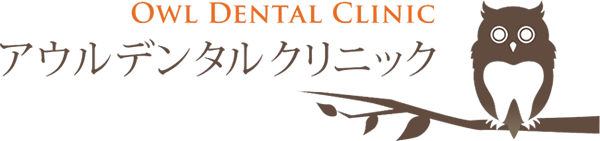歯髄温存療法
- HOME
- 歯髄温存療法という選択肢
歯髄温存療法とは?
歯髄温存療法とは、歯の神経と血管からなる歯髄を抜かずに残す方法です。進行した虫歯では、細菌感染が歯髄にまで及んでいるため、これを抜く処置(抜髄)が必要となりますが、歯髄温存療法が適応できれば、歯の神経を残したまま治療を完了させることが可能となります。
歯髄は、歯の生死にかかわる重要な組織なので、可能な限り温存したいものです。その際に有用なのが歯髄温存療法です。

歯髄温存療法の種類
間接覆髄法(かんせつふくずういほう)
間接覆髄法とは、歯髄が露出する前の段階で施術する方法です。中等度くらいの虫歯で、もう少し歯を削ると歯髄がむき出しとなる場合に、MTAセメントなどの薬剤で患部を覆います。歯髄を間接的に守ることになるため、このような名前がつけられています。
直接覆髄法(ちょくせつふくずいほう)
直接覆髄法とは、虫歯治療で歯髄が露出した段階で施術する方法です。むき出しとなった歯髄を薬剤で直接的に覆うことから、このような名前がつけられています。直接覆髄法は、虫歯治療の過程で偶発的に露髄したケースに加え、外傷で歯髄が露出したケースにも適応可能ですが、歯髄に細菌感染が起こっていないことが前提条件となります。外傷によって歯髄に強い炎症が起こっていたり、出血が見られたりする場合も直接覆髄法の適応が難しくなる点に注意が必要です。
部分断髄法(ぶぶんだんずいほう)
部分断髄法とは、歯髄の一部を除去する方法です。虫歯治療や外傷によって歯髄に軽度の細菌感染が起こっているケースが適応症となります。通常の歯科治療では、この時点で抜髄が適応されますが、歯髄温存療法に対応している歯科医院であれば、部分断髄法によって神経を残せる可能性が出てくるのです。
全部断髄法(ぜんぶだんずいほう)
全部断髄法とは、歯の頭の部分である歯冠部に分布している歯髄をすべて取り除く方法です。比較的進行した虫歯で、細菌感染の範囲も広い症例に適応されます。私たちの歯髄は、歯冠部と歯根部の2つに大きく分けられ、全部断髄法では歯根部の歯髄を温存することが可能となります。
歯髄を温存するメリット
歯髄温存療法によって歯の神経と血管を残すと、次に挙げる5つのメリットが得られます。
1.歯の寿命を延ばせる
歯髄は、歯に対して酸素や栄養素、免疫細胞などを供給する重要な組織です。抜髄によってこれらの供給が途絶えると、歯の健康状態が悪くなり、寿命も縮まります。歯髄が残っている歯を生活歯(せいかつし)と呼び、歯髄を抜いたあとの歯を失活歯(しっかつし)と呼ぶのはこのためです。
歯髄は生死や寿命を司る組織であることから、抜かずに残せることは患者様にとって極めて大きなメリットとなります。

2.歯の感覚を残せる
歯髄を抜いた歯は、痛みを感じることがなくなります。外傷で歯に強い衝撃が加わったり、虫歯が再発したりした際に痛みを感じなくなることは、歯にとって極めて大きなデメリットとなります。なぜなら歯に起きた深刻なトラブルを自覚できなくなるからです。歯髄温存療法によって歯の感覚を残せれば、ちょっとした異常も早期に自覚できるため、歯の健康を維持しやすくなります。

3.根管治療を回避できる
歯髄温存療法は、根管治療の一歩手前の治療法です。歯科的な処置を施すのは、歯の頭の部分だけに限られるため、歯髄温存療法が適応できれば根管治療は避けられます。根管治療は、治療期間が長く、再発するリスクも高く、痛みなどの不快症状に悩まされることも多いため、歯髄温存療法によって回避できることはとても大きなメリットです。

4.治療中・治療後の痛みを軽減できる
歯髄温存療法と根管治療を比較した場合、治療中・治療後の痛みは、前者の方が軽いです。なぜなら歯髄温存療法で処置を加えるのは、歯の頭の部分の歯髄に限定されるからです。

5.治療にかかる費用を抑えられる
歯髄温存療法と根管治療を自費診療という前提で比較した場合、治療にかかる費用は前者の方が安くなります。歯髄温存療法は、施術する範囲が狭く、必要となる薬剤や機材も少ないことから、経済面においても根管治療より優れているといえます。
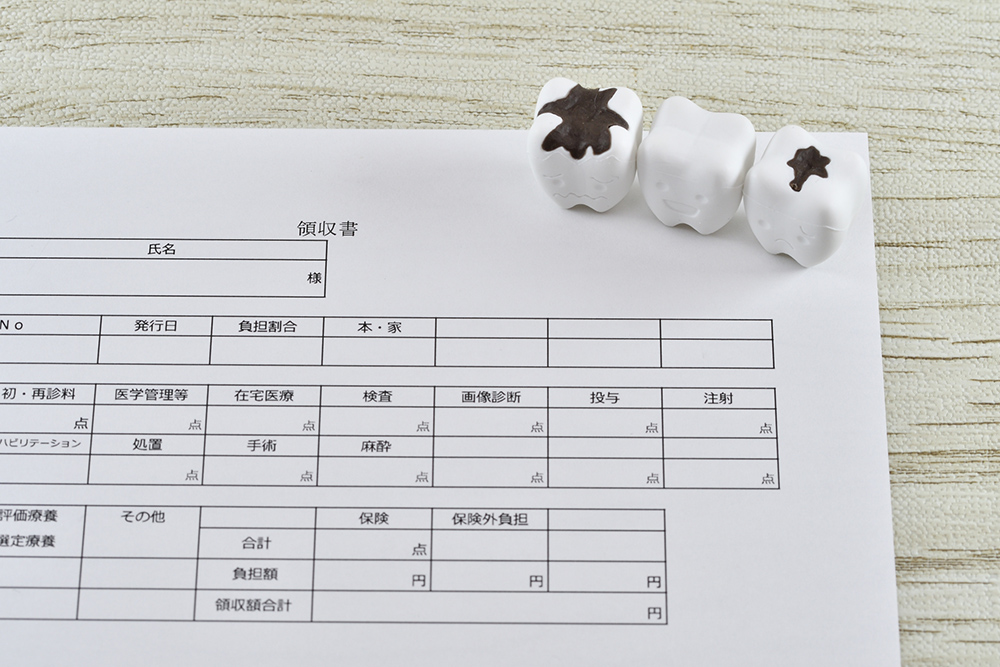
このような方にオススメです
次のような方には、歯髄温存療法が推奨されます。
根管治療を避けたい方
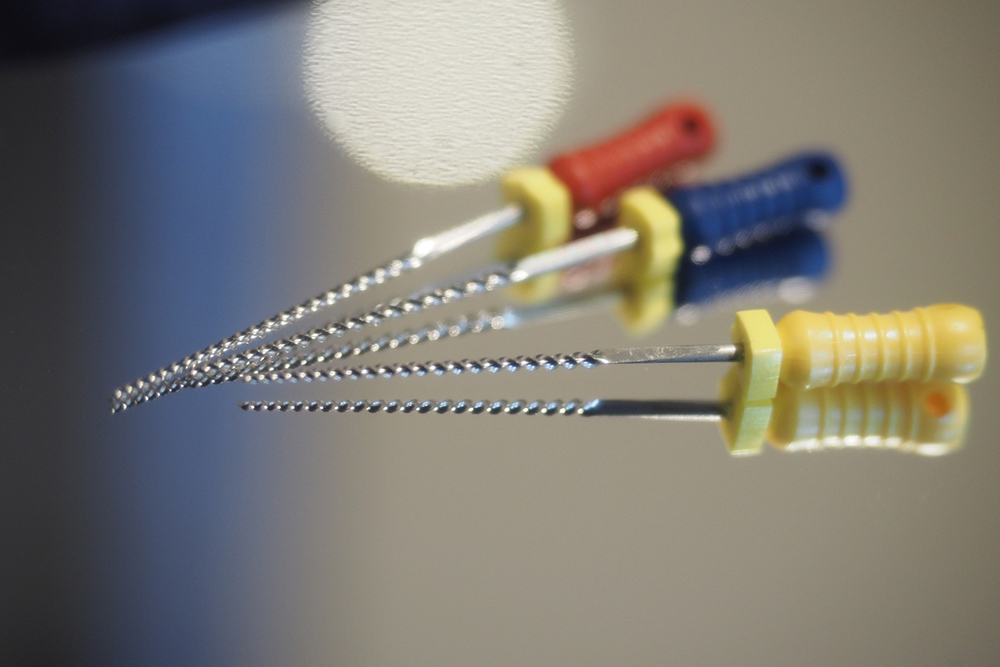
根管治療は、歯を残すための最後のとりでとなる治療です。しかしながら根管治療は治療期間が比較的長く、痛みなどの不快症状に悩まされる場面も多いです。また、根管治療が奏功しない場合は、抜歯以外の選択肢がなくなります。こうした根管治療を避けたい方には、歯髄温存療法がおすすめです。
将来的な抜歯のリスクを最小限に抑えたい

現状、天然歯に優る人工歯は存在していません。失った歯を歯根から回復できるインプラントでも、天然歯と同等の噛み心地や見た目を再現することは不可能なのです。そんなかけがえのない天然歯を失うリスクはできるだけ抑えたいという方にも歯髄温存療法がおすすめです。
歯の自然な感覚を失いたくない方

歯髄温存療法で歯の神経を全部、あるいは部分的に残すことができれば、歯の自然な感覚も保存可能です。その結果、食事の際に冷温刺激や機械刺激を感じやすくなります。また、外傷や虫歯で歯にダメージを負った際にも、異常を自覚しやすくなります。
歯髄温存療法と根管治療の違い
| 歯髄温存療法 | 根管治療 | |
|---|---|---|
| 神経の保存 | 可能 | 不可能 |
| 歯の感覚 | 残せる | 残せない |
| 治療期間 | やや短い | やや長い |
| 治療に伴う痛み | やや少ない | やや多い |
| 抜歯の可能性 | 低い | やや高い |
| 治療にかかる費用(自費) | 安い | 高い |
| 適応範囲 | 狭い | 広い |
歯の神経を全部、あるいは部分的に残せる歯髄温存療法では、神経の保存が可能で、歯の感覚も相応に残せます。この点は歯冠部歯髄と歯根部歯髄のすべてを完全に取り除く根管治療と大きく異なります。
また、歯冠部歯髄だけに処置を施す歯髄温存療法は、根管治療と比較すると治療期間が短く、処置に伴う痛みも少なくなっています。抜歯の可能性も歯冠部歯髄だけ手を加える歯髄温存療法の方が低くなり、治療費の総額も根管治療より安くなるのが一般的です。
その一方で、歯髄温存療法の適応範囲は根管治療より狭くなっています。歯髄温存療法は、細菌感染が歯冠部歯髄に限局していることはもちろん、周りの歯質の状態や虫歯の深さも厳密に診査した上で適応の可否を判断しなければならないからです。
歯髄温存療法の流れ
歯髄温存療法は、次の流れで進行します。
カウンセリング
はじめに、歯髄温存療法の特徴やメリット・デメリットについて説明いたします。歯髄温存療法は、通常の虫歯治療や根管治療とは異なる点が多々あるため、疑問や不安が残っているまま治療に進むのは良くありません。歯髄温存療法についてわからないことや気になることがあれば、カウンセリングの段階で遠慮なくお尋ねください。

検査・診断
虫歯の進行度や歯髄の状態などを諸々の検査で調べます。その結果を踏まえた上で診断を下し、歯髄温存療法の適応の可否を判断します。

感染した歯質・歯髄の除去
細菌に感染している歯質や歯髄を取り除きます。間接覆髄法に限っては、歯髄の除去が不要となります。当院では、歯科用顕微鏡であるマイクロスコープを活用した拡大視野下での精密処置を施します。

歯髄の保護
MTAセメントを始めとした薬剤で、歯髄を保護します。

歯冠の修復
歯髄の保護が完了し、痛みなどの症状も消失したら、歯冠を修復して治療は完了です。歯冠はコンポジットレジン充填やインレー、クラウンなどで修復するのが一般的です。

メンテナンス
歯髄温存療法後も定期的なメンテナンスを受けることで、歯のトラブルを未然に防ぎやすくなります。歯の感覚や詰め物・被せ物の装着感などに少しでも異常を感じたら、定期的な通院の際にお伝えください。

よくある質問と回答
-
どの歯科医院でも歯髄温存療法を受けられますか?
歯髄温存療法が受けられる歯科医院は、一部に限られます。歯髄温存療法は専門性が極めて高い治療分野なので、歯科医師であれば誰でも適切に行えるというものではないのです。歯の根の治療である歯内療法が得意な歯科医師、その分野の研鑽を積んでいる歯科医師が在籍している必要があります。
通院回数や期間はどれくらいですか?
歯髄温存療法の通院回数は、虫歯や外傷の重症度に応じて変わります。軽度から中等度の症例であれば、2~4回程度の通院で治療が完了します。重度の症例では、通院の回数がさらに増えることも珍しくありません。治療期間は、1週間に1回の頻度で通院した場合、1ヵ月くらいが目安となります。通院の間隔が広くなれば、その分だけ通院期間も長くなります。ただし、歯の状態によっては、歯髄を保護してから修復をするまでに、相応の期間を空けなければならないこともあるため、1~2ヶ月程度の治療期間を見ておいた方が無難といえます。重症例に関しては、2~3ヵ月、あるいはそれ以上の期間を要することが多いです。
虫歯が深くても神経は残せますか?
歯髄温存療法で神経を残せるかどうかは、ケースによって変わります。虫歯が深いケースでも、全部断髄法を適応すれば、歯根部歯髄は残せる可能性があります。一見すると深い虫歯でも、神経へのダメージが少ない場合は、部分断髄法で対処できることもあります。その一方で、虫歯が深すぎて歯髄温存療法の適応外となるケースも珍しくはありません。
治療中や治療後に痛みはありますか?
歯髄温存療法を行う際には、必ず局所麻酔を施すことから、治療中に強い痛みを感じることはほとんどありません。治療後に局所麻酔の効果が切れてからは、軽い痛みやうずき、違和感などが生じますが一時的な症状にとどまります。また、治療後の痛みは鎮痛剤を服用することで軽減が可能です。重症度の高い症例に歯髄温存療法を行った場合は、治療後に比較的強い痛みが生じることがあります。この点はカウンセリングや治療前の説明で歯科医師から説明があります。痛みへの対処法も含めて、よく聞いておいてください。
前歯と奥歯では治療の違いはありますか?
歯内療法(歯髄や根管への処置)という観点では、構造が比較的シンプルな前歯の方が治療しやすいです。奥歯は根管の数も多くなるため、前歯より治療にかかる時間や手間も多くなります。歯髄温存療法においても、奥歯より前歯の方が治療しやすい傾向にあります。
保険は適用されますか?
歯髄温存療法は基本的に保険適用外となります。歯髄を保護するMTAセメントやマイクロスコープ、精密診断に用いることがある歯科用CTなども保険適用外の薬剤・機材となります。